|
|
| 汎用超高速データベース処理技術―多様なデータ構造と超並列処理への普遍的アプローチRealTimeVIDP |

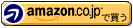 | [価格] 1680円
1500円以上国内配送料無料でお届けします。 |
| [著者] 古庄 晋二 |
| [ページ数] 159 ページ |
| [出版社] 東大総研 (2005-08) |
| [ASIN] 4902721015 |
| [サイズ(cm)] 21 × 15 |
|
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
|
 高速化技術の決定版 2005-10-03 高速化技術の決定版 2005-10-03
本書は「成分分解法」と呼ぶ新しいデータ構造とその応用について、具体的な例を用いて簡潔かつ平易に解説されており、その構造にすることで、なぜこれまで難しかった超高速性を実現できるのかといった点が、初心者にも理解しやすくまとめられいてる。
また本書の後半では、単純な2次元のテーブル構造だけでなく、木構造や超並列構造への応用についても解説されており、その適用可能範囲はかなり大きいと思える。
本書は、コンピュータ技術者だけでなく、数学やパズルに興味がある人にもお薦めしたい本である。
 日本発の新技術として注目して行きたい。 2005-10-02 日本発の新技術として注目して行きたい。 2005-10-02
私の専門は、Computer Architectureです。
特に高速化におけるデータ構造とアルゴリズムには、興味を持っています。スーパコンピュータの高速化において、データ構造とそのアルゴリズムについて勉強し、それを支える高速ハードウェアを研究した。
又、米国に駐在中には、高速データベースについてデータ構造とアルゴリズムも勉強し、試験的にDBMSも開発してきた。Relational Databaseについては、故)E.F.Codd氏が集合論を援用したデータベースを提案した。それを高速化するものとしては、精精Index,程度でしかない。ミシガン州Ann Arbor市あたりの人たちが数学を援用し新たなデータ構造とアルゴリズムの提案を細々と行っている。
今回の、古庄氏の本は、これらAnn Arbor市の辺りの人たちの提案をもっと数学的に拡張した論理を展開している点に感心している。日本でも数学を裏づけにしたデータベースの研究を行っている。
古庄氏は、Relational Databaseのみならず、Network Database, Hierarchical Database、更にはXML Databaseのデータ構造とアルゴリズムの最適化に挑戦している。
今後の技術としては、分散処理が今後の課題であり、SOA(Service Oriented Architecture),Grid Computing, Ubiquitous Computing(英語では、Pervasive Computingの方がとおりが良い)へと進歩している。古庄氏の狙うところは、この分散処理に関するデータ構造とアルゴリズムを目指しているようで、日本発の新技術として注目して行きたい。
 日本発の新技術として注目して行きたい。 2005-10-02 日本発の新技術として注目して行きたい。 2005-10-02
私の専門は、Computer Architectureです。
特に高速化におけるデータ構造とアルゴリズムには、興味を持っています。スーパコンピュータの高速化において、データ構造とそのアルゴリズムについて勉強し、それを支える高速ハードウェアを研究した。
又、米国に駐在中には、高速データベースについてデータ構造とアルゴリズムも勉強し、試験的にDBMSも開発してきた。Relational Databaseについては、故)E.F.Codd氏が集合論を援用したデータベースを提案した。それを高速化するものとしては、精精Index,程度でしかない。ミシガン州Ann Arbor市あたりの人たちが数学を援用し新たなデータ構造とアルゴリズムの提案を細々と行っている。
今回の、古庄氏の本は、これらAnn Arbor市の辺りの人たちの提案をもっと数学的に拡張した論理を展開している点に感心している。日本でも数学を裏づけにしたデータベースの研究を行っている。
古庄氏は、Relational Databaseのみならず、Network Database, Hierarchical Database、更にはXML Databaseのデータ構造とアルゴリズムの最適化に挑戦している。
今後の技術としては、分散処理が今後の課題であり、SOA(Service Oriented Architecture),Grid Computing, Ubiquitous Computing(英語では、Pervasive Computingの方がとおりが良い)へと進歩している。古庄氏の狙うところは、この分散処理に関するデータ構造とアルゴリズムを目指しているようで、日本発の新技術として注目して行きたい。
 日本発の超高速データベースのデータ構造とアルゴリズム 2005-09-29 日本発の超高速データベースのデータ構造とアルゴリズム 2005-09-29
私の専門は、Computer Architectureです。
特に高速化におけるデータ構造とアルゴリズムには、興味を持っています。スーパコンピュータの高速化において、データ構造とそのアルゴリズムについて勉強し、それを支える高速ハードウェアを研究した。
又、米国に駐在中には、超高速データベースについてデータ構造とアルゴリズムも勉強し、試作した。Relational Databaseについては、故)E.F.Codd氏が集合論を援用したデータベースを提案した。それを高速化するものとしては、精精Index,程度でしかない。ミシガン州Ann Arbor市あたりの人たちが数学を援用し新たなデータ構造とアルゴリズムの提案を細々と行っている。
今回の、古庄氏の本は、これらAnn Arbor市の辺りの人たちの提案をもっと数学的に拡張した論理を展開している点に感心している。日本でも数学を裏づけにしたデータベースの研究を行っている事を知り、感動している。
古庄氏は、Relational Databaseのみならず、Network Database, Hierarchical Database、更にはXML Databaseのデータ構造とアルゴリズムの最適化に挑戦している。
分散処理が今後の課題であり、SOA(Service Oriented Architecture),Grid Computing, Ubiquitous Computing(英語では、Pervasive Computingの方がとおりが良い)へと進歩している。古庄氏の狙うところは、この分散処理に関するデータ構造とアルゴリズムを目指しているようで、日本発の新技術として注目して行きたい。
|
|
|